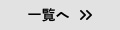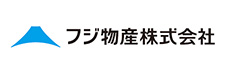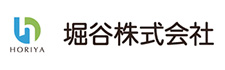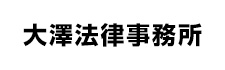-スクールのコーチをやってみて気付いた点は何かありましたか?
普通は現役を終えるとそのまま指導者になる人が多いと思いますが、僕の場合は特殊で、引退してから1度サッカーから離れて別の社会を経験したというのがありましたから、指導のスタンダードというものがわからなかったという…。ですから「もっとこうすれば」というよりは「こういうものなのだな」と自分の中で処理していましたね。でも、今思うと「ああいう場合はもっとこうすれば」ということは思いますけど、当時は指導者初体験でしたからとにかく流れに乗ってやっていた感じです。
-その他に何か感じたことはありましたか?
当時の子供たちの中には宮本航汰や、エスパルスではないですがJリーガーになった子供も結構いました。今はなかなかそういう子供が出ていないので、その頃の今泉さん(現エスパルススクールヘッドオブコーチング)の指導法というのは凄いのだなとあらためて思いますね。
-当時の宮本航汰選手はどのような子供でしたか?
宮本航汰はプロになると思っていました。やはり一番目立っていましたし、彼がいるかいないかで勝敗が決まる選手でしたからちょっと飛び抜けていました。(宮本)航汰がいるとチーム全体が強くなる感じで。今はなかなかそういう選手はいないと思いますから、当時から「この子はプロになれるだろうな」と思っていましたよ。
-水谷拓磨選手、北川航也選手、宮本航汰選手が同期としてユースから昇格しましたが、当時は宮本選手が一番だったのですか?
スクールには(宮本)航汰しかいませんでしたけど…。(北川)航也もスクールにはいなかったですが、その存在は知っていました。ただ特徴もポジションも違いましたし、どちらが上手いとかは比べられませんよね。でも、近くで見ていたので航汰は小学生としてはスバ抜けた選手でしたよ。航汰は性格が遠慮がちだったのでもっと性格的にガツガツしていたら、日本代表にも選ばれてもおかしくないと思いますけどね。
-スクールのコーチをやってみて、その上のジュニアユースやユース、トップチームのコーチは目指さなかったのでしょうか?
サッカーから離れていたブランクもありましたし、「指導者」というものに対して自信がなかったというのが正直なところです。だから、上の年代よりも小学生への指導の方が自分としては合っているのかなと感じていました。一度、中学生の指導もやったことはあったのですが、何かしっくりこなかったということもありましたので。
-小学生と中学生の違いというのは?
小学生は吸収が早いというか、ちょっとしたことで、もの凄く変わることがあって…それが面白いですよね。そこにやりがいを感じていました。
-その後には三島U-12などの監督もやられていますが?
正直、「スクール」と「チーム」という違いがよく分からなくて…。スクールが長かったのでチームを任されたのですが、ちょっとピンとこなかったのですね。チームとなると試合があって、SS富士が最初のチームでしたがそこは中学生だったのですね。それまでスクールは練習が主でしたから、ちょっとその違いに戸惑ったというか…もちろんチームで試合するのも楽しかったですけど。
指導者を目指す人は基本的にはチームや監督をやりたい人がほとんどですけど、自分はそういうものはなくてスクールで指導しているのが楽しかったのですが、実際にチームを任されてやってみるとチームにはチームの面白さというものがあるのに気付かされたというか「こういうものもあるのだ」と思いました。ただ、SS富士を4年間やったあとに育成部から声を掛けられてそのU-12三島へ行ったのですが、富士に比べると選手の質も高かったですし、富士の時はスクールもやりながらチームもやっていたのですが、三島は管轄が育成部になるので、チームオンリーでしたからちょっと違いましたね。
-「チーム」というのは勝つことが目的のような練習だったのですか?
子供たちはやっぱり試合をやれば勝ちたいですし、そういう気持ちも大事なのですが、育成年代ですからその選手の特徴を伸ばすとか生かすこと、そしてポジションやその適性を見出すことが大事だと思っていました。できないことをやれるようにすることもありますが、今できていることを更に強化してあげて本人に自信をつけさせることの方が僕は面白かったですね。
-その他には何か思うことはありましたか?
クラブは少人数ということで良い部分でもありますけど…。今、高体連が強くなっていますが、強豪校と言われる学校では何百人という部員がいて、チームもA、B、Cと複数あって、その中で競争をしています。Aチームから落ちる選手もいれば、BチームからAチームに昇格する選手もいて、その競争を勝ち抜くという意味でのメンタルは凄いと思います。海外などはクラブチームのユースでも1年で戦力外になってしまう選手もいるほど競争が激しいわけです。ただ、今のクラブの下部組織だと3年間は保証されるわけで、もちろんその中でも競争はありますが、高体連の強豪校や海外に比べるとどうなのかなとは思います。
-下部組織はトップチームに優秀な選手を供給する役割ですが、その中で試合では勝利を求められますか?
勝ちながらタレントを育てるというのは難しい作業になります。勝利するためにはチームとして戦うことになりますけど、そこの「チームとして」という部分が強くなってしまうと、個の部分が伸びなくなってしまうこともあったりしまして…。その両方を求められますからなかなか難しいのだと思います。一応、クラブからは「勝たなくても良い」と言われますけど、なかなかそういうわけにはいかないですよね。
-そうすると和田さんが監督をやられていた時のやりがいというものは何でしたか?
そうですね。やっぱり選手が育ってくれることが一番のやりがいでしたね。
-昔の中学校のサッカー部や野球部などは毎日遅くまで活動していたと思いますが、今はそこまでやれない状況になっています。そこはどう思われていますか?
サッカー以外の部活動についてはわからないですが、サッカーに関しては棲み分けができてしまっていますよね。将来プロになりたいとか、上を目指す子供はクラブチームや町クラブへ、逆にそこを目標としない子供は部活に入るというスタイルになっています。その分お金はかかってしまうというマイナス要素はありますけど、それが確立されていますね。
-早くからプロサッカー選手を目指す子供はそれで良いのかもしれないですが、まだその才能に気付かない子供の発掘という意味ではサッカー界にとってはマイナスなのではないですか?
ただ、トレセンやクラブチーム、町クラブ、いろいろなクラブが今はありますからそういった隠れた才能も拾えているのではないでしょうか。昔みたいに部活ということだけだと選択肢がいくつもありませんから、逆に才能が開花する前に別の道へ行ってしまうこともあったと思いますよ。今なら各クラブの特徴などもいろいろですから、自分にあったサッカー環境でやれることはプラスだと思います。ただ、気になることがあるとすれば学校が終わってから各クラブチームへ参加するということで、終わる時間が遅くなってしまって食事や睡眠などにも影響が少なからずあるのではと思っています。実際にクラブチームに所属する子供よりも、中体連の子供の方が身長も高い選手が多いような感じはしています。
-体格差が出てしまっていると?
そうですね。食事はしているけど栄養が上手く回っていないとか栄養以上に運動量が多いとか…。海外のクラブチームの場合などは長期休暇が長く与えられるので、地元に戻ると太って帰ってくる子供が多くてそれがまた練習でスリムになって成長するみたいなことがありますけど…。それでも日本代表などを見ると大型の選手も多いですし、世界との体格差というのも縮まっていますからそこまで心配しなくてもよいのかもしれないですね。
-そのU-12の監督も2022年で辞められていますが?
自分の将来を考えた時に…。しっかりとライセンスを取ってトップのコーチやゆくゆくは監督にという考えがあると思いますけど、僕の場合はジュニアユースやユースを担当していたので、このままで良いのではと考えたところがあります。最初はエスパルスのためにということでやらせてもらったのですが、これから10年先、ある程度の年齢に達した時にどうなっているのかなと。このままこのポジションに居座っていて良いのかと考えましたね。正直、これまで「流れ」でいろいろなことをやって来ていて、真剣に「将来」について考えたことがなかったので…。
-そうすると将来のことを考えて退職したということですか?
そうですね。家族を持って子供が生まれて初めて「将来」について考えましたね。このまま続けてどうなるのかということを。
-ちなみに子供の頃、将来はどのような職業に就きたいというのはありましたか?
子供の頃は野球選手でしたね。父親が野球をやっていましたから保育園の記念誌を見ると「将来は野球選手になる」と書いていました。でも、小学校になったらやっぱりサッカー選手に変わっていましたね。
-そしてエスパルスを退職して平松さんが経営している施設の職員になられたわけですが?
そうですね。エスパルスを辞めようと考えている時に松ちゃん(平松康平)と話をしている中で、以前から「一緒にやらないか」と誘ってはもらっていました。現役が終わってサッカーを離れて、またもう1度サッカーに携わって、これを極める選択肢もあったのですが、また別な道を行こうと決めました。
-障がいのある子供たちと過ごす「放課後等デイサービス」の仕事はいかがですか?
今、勤めている「BAILA」という会社には、
・興津という地域を生かした海・山・川と自然豊かなロケーションで活動する小学校低学年を対象とした「みらいがくいん」
・パソコンや調理、川遊びなど経験・遊びから社会性を育て自立につなげる活動をする小学校高学年から中学生を対象とした「フォルマ」
・今後の自立生活を実現させる為に生活技術の向上を目的とした短期入所(ショートステイ)の「カバナ」
という3つの施設があります。それと同時に今は1週間に1日だけですけど「障がいがあってもスポーツができる場を」というテーマでスポーツクラブの「バイラ」という取り組みもやらせてもらっています。そのスポーツクラブでは体幹トレーニングや走り方など、もちろんサッカーもやるということで興味がありました。
-平松さんから誘われた時はどういう印象を持ちましたか?
最初は全然ピンとこなかったですね。わからない世界というか今までそういうことに携わったことがなかったので…。確かにスクールなどで子供たちとは接していましたけど、それはあくまでも「サッカー」が中心にありましたから。松ちゃんは小学生の頃に知り合ってそこからの付き合いだったので信頼はしていましたから、そういう風に誘ってくれるのであればやってみようかなと思いました。
-平松康平さんとは子供の頃からのお付き合いだと思いますが、和田さんから見てどのような方ですか?
そうですね。今は経営者としていろいろなことに取り組んでいますが、昔からブレはないですね。ちゃんと1本スジが通っているというか、「良い人」という意味ではなくて「生きざま」がしっかりとしているので僕もずっと付き合わせてもらっていますし、今は仕事も一緒にさせてもらっています。松ちゃんはいろいろと面白いですよ。だから面白みがなくなったら一緒にいることをやめるかもしれないですね。でも、多分一生面白いと思いますよ。
-社長としての平松さんはいかがですか?
やっぱり、人柄というか…。じゃあ凄くキレ者でできる社長かと言いえばちょっと違うかもしれないですけど、でもそういう人間性、そこをどうにかして手伝いたくなる人というか、一緒にやりたくなるというか…。みんながそれに引き寄せられてしまうような人柄なので、今一緒に働いている他の職員などもそういう何とも言えない魅力に吸い寄せられたのだと思いますよ。

次回へ続く